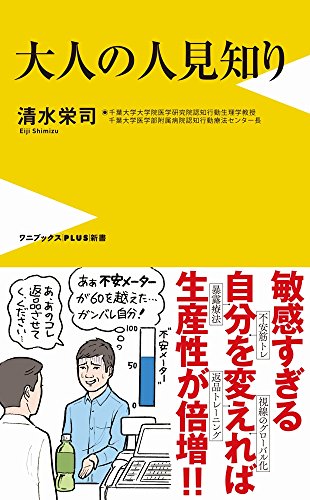はい、またまたわたしです。
『大人の人見知り』<清水栄司> (ワニブックス)
ささっ~と、あのあとこちらの本を読み続けることができました!
これまで「社交不安障害」の本は途中から薬物療法や診断の方法など専門的になることがありましたが、
こちらの本は「身近な具体例」が多く盛り込まれていて、大変わかりやすく(共感多く)読みやすかったです!
■本を読んで感じたこと、考えたこと、思ったこと■
~「たったひとつの出来事からの支配力」~
社交不安障害の事例を通じ感じていること。
自分の実体験でもそうですが、「たったひとつの出来事からの支配力」ということを感じています。その支配力がすべてのことに不安や否定的なことを作っている。
もはや「たったひとつの出来事からの後世に延々と引き継がれる祟り」くらいのイメージかも(?)←あくまで当事者の個人的な感想です。
脳内の中にはそのくらいにわたって住み着いている印象かな?🏠
■認知の歪み■
本の中では「認知の歪み」というwordが度々現れます。
わたし自身、プロの方に「認知行動療法」をしていただきたいと思っているところです。ゆっくりそういう場所を探して見つけたいなと思います。
今はそういう本で1人で学べる範囲で情報を増やしています。
■ピーク・エンドの法則■
P88に「ピーク・エンドの法則」のわかりやすいたとえがありました。
なるほどね!と思いました。人の記憶の作られ方がわかりました。
併せてP89には「リスクリプティング」というwordが紹介されています。
自分の記憶→記憶という脚本を書き換えていく
この作業が紹介されています。
新しい知識との出会いです🎬
■「人見知り」という自覚■
先ほどもお伝えしましたが、背表紙だけではスルーしてしまっていただろう本の世界にわたしが癒される情報がたくさんありました。
前回「あがり症」という切り口からの本も紹介しましたが、
どこから入るかによって一番求めていた情報との出会い方が決まりますね。
例えば本屋さんに行って「社交不安障害」というwordだけで本を探したところで、
自分に「人見知り」「あがり症」の自覚がなければずっと通り過ぎていたと思う。
「えっ?あたし、人見知りじゃないし~」みたいな。
ところがどっこい本の内容を読めば、
見事に自分にあてはまることがちらほらと存在するということ。
反対に「人見知り」「あがり症」という悩みのある方は、自然に入りやすい形で社交不安という世界に入って行けるともいえるなと感じました。
■本屋さんと図書館■
ちなみにわたしが知る範囲で本屋さんのそういった精神のコーナーには、社交不安に関する本はありませんでした。そのジャンルで多くあるのは「うつ」に関する書籍でした。
やっぱり図書館はレパートリーが多いというか、より踏み込んだものも多い印象です。
今回は図書館の検索ページから、
「社交不安」か「認知行動療法」のどちらかで検索してこの本と出合えました。
■頑なにスタートしない呼吸法■
さまざまな精神に関する本でご紹介される「呼吸」のエクササイズ。
全くしようと試みないわたしです。
ごくたま~に意識するかな。
結構「呼吸」が大切なのだなと思うのだけど、自分からはアクションを動かせないままですね。ご興味がある方はぜひ!
わたしは今は興味を持てていないのが現状です。
■じゃあ誰に話すんだよ(自分への問いかけ)■
P152に著者の言葉で
「社交不安症の方は~医師にも不安を感じてしまい率直に自分の悩みを言えないことが多いのです。」と書かれていました。
わたしはこの部分を読んだときに、
「そうです。そうなんです。先生!!」って思いましたし、
そうであっていいんだというか、そういう状態もやっぱりあるよね?って思いました。
ちょっと気が楽になりましたね。
同時に専門的な先生にも詳しく自分のことを話せないなら
じゃあ誰に話すんだよ、とも自分につっこみましたね。
と、長々といろいろとこの本を読みまして、
自分の中から少し何かを引き出せてもらえた感が少しあります。
(少しずつ)
最初読み始めた時は
これ借りたけど「絶対うちには関係ないわ~」くらいの距離感だったかもしれない。
それがプロローグで一気に近いものを感じたっていう気分です。
ありがとうございました。
それでは、また会いましょう🔎